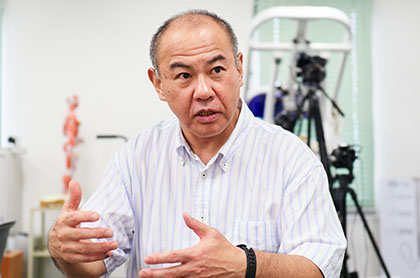- 高校生Webキャンパス
- 研究
- 人間福祉学部
- 河鰭一彦 教授


「古賀稔彦君」に投げられて・・・決めた学究の道
人間福祉学部河鰭一彦 教授【後編】

「小よく大を制す」スポーツ科学で解明したい
9歳から柔道を始め、将来は柔道で食べていこうと思っていました。日本体育大学の柔道部時代は身長約1・8㍍、体重約100㌔。実業団から誘われ、そこそこ自信がありました。4年の時、後にバルセロナ五輪で金メダルをとる古賀稔彦さんが入部してきました。既に五輪候補に選ばれていたとはいえ、第一印象は「小柄だな」。なめてかかり、乱取りでいきなり投げたところ、怒りましてね。5分間ひたすら攻め込まれ、最後は思い切り畳にたたきつけられました。「こういうやつが柔道で飯食うんだな」と、心が折れましたよ。同時に、大きくて筋力もある人間が小さな相手に組み負ける理由を知りたくて、石井喜八先生の下でスポーツ科学を学ぶことにしたのです。
計算もデータもスポーツ現場で役立ってこそ
石井先生のゼミは日体大で一番厳しく、徹底的に実験の基礎を仕込んでいただきました。今の自分があるのは、あのときに鍛えてもらったおかげです。「スポーツを研究する人間は実践ができなければダメだ」という教えを、スーパー専門家の多い関学に来てから、特にかみしめています。今一緒に研究している理工学部人間システム工学科の先生方には、数値計算やデータ解析においてはかないません。でも、力の出し方は実際にこうするんだとか、この力の出し方が柔道のこういう場面で役立つということが私には分かる。それが武器なんです。昔と違い、さすがに今は「体育の先生は頭も筋肉でしょ」なんて言う人はいませんし、工学や生理学の先生とはよく研究の話をしています。
最新鋭マシンのトレセンで競技能力アップ
キャンパスの中でよくのぞくのは、学部棟からすぐ行けるトレーニングセンターです。私が考えて基本的なコンセプトを継承してくれている施設で、競技能力の向上を測るため、ベンチプレスやチェストプレスなど、マシンには最新鋭のものをそろえています。学生にできるだけ使ってほしいので、見には行っても自分ではほとんど使いません。バドミントンや水泳の授業と同じで、先生がやると、学生は自分の活動をやめてしまうんですよ。学内にいるときは、時間があれば実験室で実験しています。体育の教員の特徴だと思うんですが、仕事と趣味が別個じゃないんです。関学には測定機器もいろいろ買っていただきましたし、私にとって実験するのは当たり前で、楽しいことなんです。