- 高校生Webキャンパス
- 研究
- 教育学部
- 原田大介 教授


変わるべきはマジョリティ
教育学部原田大介 教授【後編】

私のこれまでと、インクルーシブ教育
私には、吃音と発達障害(高機能自閉症とADHD:注意欠如・多動性障害)があります。子どもの頃は吃音のために自分の「はらだ だいすけ」という名前を言うことができず、からかわれたものです。ADHDの特性の一つである「注意力の持続の欠如」のために、特に言語の面で記憶を維持することが困難であったために、生活全般において不便な思いをしてきました。指導教員や仲間の支援・協力もあり、大学院生のときに吃音の当事者研究に挑み、学会で発表しました。このことが社会的マイノリティ(少数派)と教育問題とをつなげて考える契機となり、通常の学級に在籍する子どもたちには多種多様な身体や生活背景があることがわかりました。インクルーシブ教育とは、多様性を包摂する教育を意味します。私が国語科教育とインクルーシブ教育をクロスさせて研究するようになった背景には、通常の学級で悩み苦しんできた私の怨念とも呼べる(笑)、思いや願いがあります。
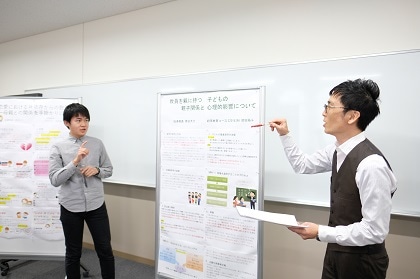
ひとりの人間にある複数の社会的特性とは?
私が研究で扱う概念に、マジョリティとマイノリティというものがあります。マジョリティは社会的多数派で、マイノリティは社会的少数派を意味します。ただし、数の問題だけでなく、マジョリティには権力強者、マイノリティには権力弱者という意味があります。また、ひとりの人間には、複数のマジョリティ性と複数のマイノリティ性とがあります。たとえば私の場合、吃音や発達障害があります。定型発達者(いわゆる健常者)をマジョリティの側に位置づけるとすると、私はマイノリティの側面があると、ひとまずは言えるでしょう。しかし私は社会的には「男性」であり、現在は「成人」でもあるため、「女性」や「子ども」と比べると、権力強者としてのマジョリティであることも事実です。誰かを「単一の」マイノリティやマジョリティに位置付けることはできません。「ひとりの人間にある複数の社会的特性」を、一つひとつ、それらの関連性も含めて丁寧に見ていくことが求められます。

研究することのやりがいと、知的なおもしろさ
この話は、インクルーシブ教育の研究にも同じことが言えます。たとえば通常の学級で言えば、発達障害、多様な性、多様な家族、外国とのつながり、貧困、虐待やDVなど、教育的な支援を要する子どものニーズを見極めることが、まず何よりも重要です。さらにそこに、場や状況、関係性に依拠する権力強者と権力弱者という視点を加えることにより、誰が、どの文脈で、何を得て、何を失っているのかを見極めることも必要です。実際のいじめの場面で見られるように、いじめられる側が常にマイノリティであるわけではない(マジョリティも巻き込まれうる)ことを考えれば、流動的な権力の視点を取り入れることの必要性がわかります。加えて学校教育の場では、子どものニーズや権力をめぐる諸問題を踏まえた上で、国語科の教育内容や方法のあり方が検討されなくてはなりません。とても難しいことですが、ここに私は国語科教育とインクルーシブ教育とをクロスさせて研究することのやりがいと、知的なおもしろさを感じています。







